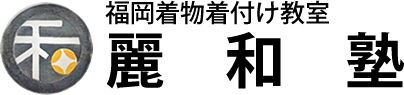譲り受けた着物・リサイクル着物の安心チェックと活用法
着付け教室福岡 麗和塾 内村圭です。
ご自宅の箪笥の奥に、長年眠っていた着物はありませんか?
あるいは、ご家族やご親戚から譲り受けた一枚、リサイクルショップや骨董市などで手に入れた着物をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。そうした着物たちは、どれもそれぞれにストーリーを持ち、時を経て今のご自身のもとへとやって来た「ご縁の品」です。
しかし、そのような着物は、「一体この着物はいつ仕立てられたものなのだろう?」と首をかしげた経験はないでしょうか。仕立てた年数が明記されていることは少なく、譲り受けた場合には、正確な情報がまったくわからないことも珍しくありません。

着物は“親・子・孫”の三代にわたって受け継ぐことができるとされるほど、優れた耐久性を持つ衣服です。しかし、三代ともなると30年、50年、あるいは80年以上前のものもあります。また、リサイクル着物の中には、明治・大正・昭和初期に仕立てられたものも含まれていることがあり、その経年は想像以上に長い場合もあるのです。
こうした着物を、安心して美しく着こなすためには、まず状態のチェックが欠かせません。特に注意すべきは、「糸の劣化」です。生地そのものはしっかりして見えても、縫製に使われている糸が経年によって劣化し、着用時に思わぬトラブルを招くことがあります。
見た目にはわからないこの“糸の弱り”を確認するには、着物の「下前の衿先」や「下前の裾」など、目立たない部分で確かめてみましょう。軽く力を加えただけでプツプツと糸が切れるようであれば、それは劣化が進んでいるサインです。また、すでにほころびが見つかる場合には、そこだけ補修しても、次は別の場所が裂けてしまうというように、連鎖的なトラブルにつながる可能性があります。
私自身も、リサイクル着物を購入し、帰宅後に自分の寸法に仕立て直そうとハサミを入れたところ、糸が弱く、すべてを縫い直さなければならなかったという経験があります。見た目に美しい反物や着物であっても、中身は予想外に脆くなっていることもあるのです。
特に怖いのは、「着物で外出したそのとき」に破損が起きるケース。
例えば、お出かけの途中でお尻のあたりが裂けてしまう、袖が外れるといった事例も、決して珍しくありません。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、糸の状態を確認するというのは、とても重要なプロセスです。
一般的に、生地そのものよりも先に糸の方が劣化することが多いとされています。つまり、生地はまだまだ着られる状態であっても、縫製糸が耐久性を失っていることで、着物全体の寿命が縮んでしまうということも起こり得るのです。
ですが、ご安心ください。
糸が弱っていることが判明しても、それは「もう着られない」という意味ではありません。むしろ、新たに仕立て直すチャンスとも言えます。仕立て替えをすることで、新しい糸を使い、ご自身の体にぴったり合った寸法の誂え着物に生まれ変わらせることができるのです。
さらに、形を変えることで新たな用途を持たせることも可能です。
例えば着物から羽織へ、あるいはコートへ仕立て直すことで、日常の中でもより取り入れやすい装いとして生まれ変わります。薄手の素材であれば、長羽織や道中着にして、洋服の上から羽織るスタイルにアレンジするのも素敵です。
また、仕立て直すことで気持ちも新たになります。
譲り受けたものや古いものに、自分の好みや生活スタイルを反映させることで、「私の着物」として再び息を吹き返すような喜びが生まれるのです。
着物は、仕立てて終わりではなく、時間とともに手を加え、繋いでいく文化です。
一枚の着物が、何度も仕立て直されながら三代、四代と引き継がれていく――
それは単なる衣服としての役割を超えた、「時間と想いの継承」とも言えるでしょう。
せっかくご縁があって手元にやってきた一枚。
どうかその着物を大切にし、安心して着ていただくためにも、まずは状態の確認から始めてみてください。
糸の強度をチェックし、必要であれば仕立て直しを検討する。
それによって、着物は再び活躍の場を得ることができます。
そしてそこから、また新しい着物の物語が始まるのです。
「大切に着る」という行為そのものが、着物に宿る記憶を未来へと紡いでいくことなるでしょう。